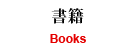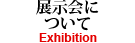明けましておめでとうございます。
日本外食新聞は12月25日号と1月5日号の合併号として1月1日新年号を発行するため、1月5日号は休刊となります。ご了承ください。
今年も本紙をどうぞよろしくお願い申し上げます。
若い飲食店経営者どんどん巻き込む
若手とベテランの良きマッチングを
(一社)日本居酒屋協会 5代目会長 大林 芳彰 氏
トップ記事
【特集】
「培養肉」「培養魚」時代はすぐそこに
「バイオ×食」の最新動向を追う
世界の人口が増え続け、気候変動が進むと畜産などの生産量が追いつかなくなり、2030年頃に肉や魚などから摂取しているたんぱく質の需要と供給のバランスが崩れる「タンパク質危機」が到来すると予測されている。
その対策の1つと目されているのが「培養肉」や「培養魚」だ。海外の一部の国ではすでに販売されており、日本でも法律が整えば、今年中にレストランで食する機会が訪れるかもしれない。
本紙2022年1月1日号では「培養肉」を取り上げたため、今回は「培養魚」を中心に「先端技術と食」の最新動向を伝える。
一般的に肉や魚の細胞を増やして作った食品を「培養肉」や「培養魚」と呼んでいるが、これは俗称であり正式名称はまだ存在しない。国際連合食糧農業機関は、「生きた細胞」に栄養(穀物由来の糖やアミノ酸など)を直接与えることで肉や魚の細胞を培養することを「細胞農業」と呼び、そこから作られたものを「細胞性食品」と呼んでいる。日本政府もこれに倣って公的文書などでは「細胞性食品」との呼び名を採用している。
海外では「細胞性食品」の実用化に向けた研究開発が急速に進んでおり、シンガポールでは米・ベンチャー企業GoodMeat社が開発した細胞性鶏肉を使ったチキンナゲットがすでに販売されている。
米国でも、同社とUpside Foods社の細胞性鶏肉について米国食品医薬品局(FDA)が安全性を確認済みで、両社に対して「細胞培養チキン」というラベルの使用を承認した。
一方日本では、以前、本紙で取り上げたインテグリカルチャーなどのベンチャー企業が「細胞性食品」の研究を進めているものの、まだ実用段階には至っておらず、法制度も整っていない。
このままでは海外に後れを取ることが危惧されるとの危機感から、2022年12月、日本での細胞農業のルール作りなどを研究していた細胞農業研究会を発展させ、細胞…
その他の主な記事
○マルハンがMUGEN買収
株式80%取得し飲食事業の中核に
富裕層向け観光事業に必要不可欠
○ねぎしFSの人材採用から定着まで
「良い店」実現が人員充足の肝に
○近藤隆ダイキチシステム新社長に聞く
《大吉》よ、どこに行く?
○日本外食新聞 年イチ経済講座
第一生命経済研究所・嶌峰義清氏が斬る
激動時代に見えた外食業界の針路
○ホットランド、釜飯とそばの新業態
○ココロオドル、昭和と令和を融合させた
ネオ和食居酒屋を立川に
――ここだけではご紹介しきれない、飲食関係者必読の最新情報をたっぷりお届けします!
連載
印束義則の繁盛店実況中継
~日常の“気づきの視点”を鍛えるセミナー~
第9回“細かすぎる”インヅカナイト詳報1
詳細・購読はこちらから ↓ ↓ ↓
★「日本外食新聞」紙媒体の申込み
https://shinbun.gaishoku.co.jp/form/
★電子版アプリの申込み(android)
https://bit.ly/35PXYOD
★電子版アプリの申込み(iOS)
https://apple.co/35PZtML
■中小外食ユーザー向け専門紙《日本外食新聞》
注目の店・企業・メーカーを徹底大解剖。
外食産業に携わる方々に有益な情報をタイムリーにお届けします。
https://shinbun.gaishoku.co.jp/
■外食産業情報の日刊専門紙《外食日報》
創刊30年を超える【実績】と【信頼】
外食企業の経営者が認める業界新聞
https://daily.gaishoku.co.jp/
■飲食店向け情報サイト《FOOD FUN!》
https://foodfun.jp/
■SNSで最新情報発信中です